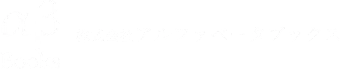書店のデジタル化で失われたもの
僕は若い頃、書店員でした。
初めて書店員になったのは、自分でも「もうそんな昔のことだったのか!」と驚きますが、もうかれこれ、26年以上も昔の話です。
初めて働いた書店、それは創業が明治2年の、当時創業120周年になったという本当に歴史のある老舗大手書店、丸善の本店、日本橋丸善でした(当時丸善で働いていた人は「丸善日本橋本店」とは言わず、「日本橋丸善」と言っていました。歴史の重み、誇りを持ってそう言っていた人もいたように記憶しています)。
まだ当時私は20歳に満たない若造で、シンガーソングライターを目指して、様々なアルバイトを掛け持ちしつつ、夜はライブハウスで歌っている日々でしたが、当時20ヶ所近くバイトをしたなかで、一番しっくり自分に馴染んだのが、この丸善の書店員の仕事でした。
まあ、当時はフリーターとかプータローとか、いろんな言われ方をしていましたが、親元にいてフリーターをしていたわけでもなく、18歳の時に家を出て練馬で一人暮らしをしつつアルバイトで生計を立てていたので、フリーターといっても毎日朝から晩まで仕事をする日々でした。丸善も、早番か遅番かというシフトに入らず、「フル番」ということにしてもらって、開店から閉店まで、それこそ正社員より長時間、毎日働いていました。
まあ今から思えば、正社員より長時間働いているなら、正社員になってしまえば給料ももっと上がるのだから、そうすればよかったのかもしれませんが、当時はシンガーソングライターを本気で目指していたので、「正社員になったらサラリーマン、夢を諦めることになる」と、馬鹿みたいに自分に言い聞かせていたこともあって、「正社員にならないの?」という誘いも断っていました(今では丸善はじめ大手書店でアルバイトから正社員になるのは至難のわざだと思いますが、当時はまだ景気が今よりもずっと良くて、なろうと思えばなれた時代でした。実際、丸善のあといくつかアルバイトを点々として行き着いた文教堂書店では店長推薦で正社員になることができましたし)。
当時はまだPOSレジもなく、さらにバーコード読み込みすらできなかったので、お客さんが本を複数抱えてレジに来られた場合は、「明細お願いします」といって、レジ係に向かって大きな声でジャンル名と定価を読み上げて、それをレジ係が打ち込んでいくというシステムでした。「1200(円)ビジネス、680実用、680文庫、780新書」てな具合だったと思います。新人だと微妙で分かりづらいジャンルの本が来ると、なんでも「実用」にしてしまったり、日経文庫が来ると混乱したりして(日経文庫は「文庫」と言っても判型は「新書」の大きさで、ジャンルは「ビジネス」という、「どれが正しいんじゃ!」と新人がレジに言うときにとても混乱させるシリーズでした)、そういうわけで、当時はかなりいい加減なレジ打も混じったジャンル別の売り上げデータになっていたような気がします。
在庫検索も、今の書店のように、探している本の陳列してある棚の位置まで表示されるような検索機は当時は置いてなくて、「在庫有」か「在庫無」ぐらいしか出てきませんでした。しかもそれもバーコードが無い本が当時はまだかなりあって、そういう本はタイトルや著者がちゃんと在庫データ化されてなくて、かなり信頼性のない在庫データだったので、とにかくお客さんに「ナニナニという本探してるんだけど、ある?」と聞かれたら、とにかく棚に在庫があるかどうか、探しに行かなくてはなりませんでした。
とにかく新人の頃は大変でした。棚に探しに行くと言っても、タイトルとか著者だけ言われても、どのジャンルの棚に探しに行ったらいいかすら分からない本ばかりでしたから。当時は日本橋丸善には、本当にたくさんのお客さんが来て、毎日の売上も全国トップクラスで凄まじいレジの混み合いでしたし(忙しい日は開店から閉店までレジに行列ができない時間がほとんど無いこともあった。これマジ本当です)、社員の人数も今の時代に比べればかなり多かったのですが、それでも何もかもアナログだったので、いろんなことに手間がかかって忙しすぎて、他のメンバーに本を探すことまで振ってしまうことも憚れかれたので、とにかく必死でお客さんに「ちょっといつまで探してんだよ!」と時にはイラつかれつつ、散々待たせて結局見つからないこともよくあって、本当に毎日汗をかきかき、あらゆるジャンルの本のタイトルや著者名と、それがどのジャンルの何処の場所に置かれているのかを、体を使って頭に叩き込んで覚え込んでいきました。
毎日毎日、そういう努力をしているうちに、一年もすると、7割ぐらいの本は、お客さんに場所を聞かれると、どのジャンルの棚のどこらへんに置いてあるのか、だいたい見当がつくようになってきました。
お客さんから「ダレダレの書いたナニナニの本を探してるんだけど」と聞かれると、「こちらです!」と検索機も使わず、その本がある棚まで、まっすぐに歩いていって、「お探しの本はこちらの本ですね?」と、まっすぐその本に手をのばし、棚から取ってお客様に手渡すと、何人かに一人は、「すごいね! こんなたくさんの本な中から、よくわかったね。さすがだね! よく棚の細かい位置まで把握してるね!さすがプロだ」と褒めたり喜んだりしてくれて、それが嬉しくて書店員をしていたようなもんでした。
あれから四半世紀の月日が流れ、今ではほとんどの大型書店ではデジタルで在庫が管理され、棚位置まで表示される時代になりました。
でもそれによって、必死で探して本のある場所を覚えることは少なくなり、当然必死で探すと強く記憶に残り自分の中に蓄積されますが、データでは、即在庫の有る無し、棚位置も分かりますが、その本の印象は記憶には残りにくく蓄積されず、もしかしたら、しばらくすればその本の存在すら記憶に残らない時代になってしまうのではないかと、私は思ってしまいます。それはやはりデジタル化によって失われた弊害なのかもしれません。
デジタル化によって失われたものは、書店員の本に対する記憶だけでなく、お客様と書店員の交流も減ってきているのではないでしょうか、などとオジさん化した僕は思ってしまうのです。四半世紀前は確かに本を探すのは大変で不便だったかもしれませんが、本を探すことで、よく聞かれる本は強く記憶に残りましたし、お客さんから感謝されることで接客の仕事の喜びも覚えました。本をお客様に手渡した後に、見つけてもらった喜びのお礼の言葉だけで終わらずに、その本をなぜ探していたのかを書店員の僕に語ってくれるお客様もいました。その話に感銘を受けて、そのあと自分でもその本を買ってしまったこともあったぐらいです。
デジタル化で失われたもののなかには、失う必要のない本当に大事なものがあったのではないかと思う、今日この頃です。
(※この記事は、かつて僕が別の場所で書いていたブログを加筆修正した復刻記事です)
この記事の執筆・監修者
春日俊一(かすが・しゅんいち)
株式会社アルファベータブックス代表取締役。埼玉県生まれ。
若い頃はシンガーソングライターを目指しながらフリーター。その後、書店員、IT企業、出版社の営業部を渡り歩いたのち、2016年にアルファベータブックスに入社。2018年に事業承継して代表取締役に就任。